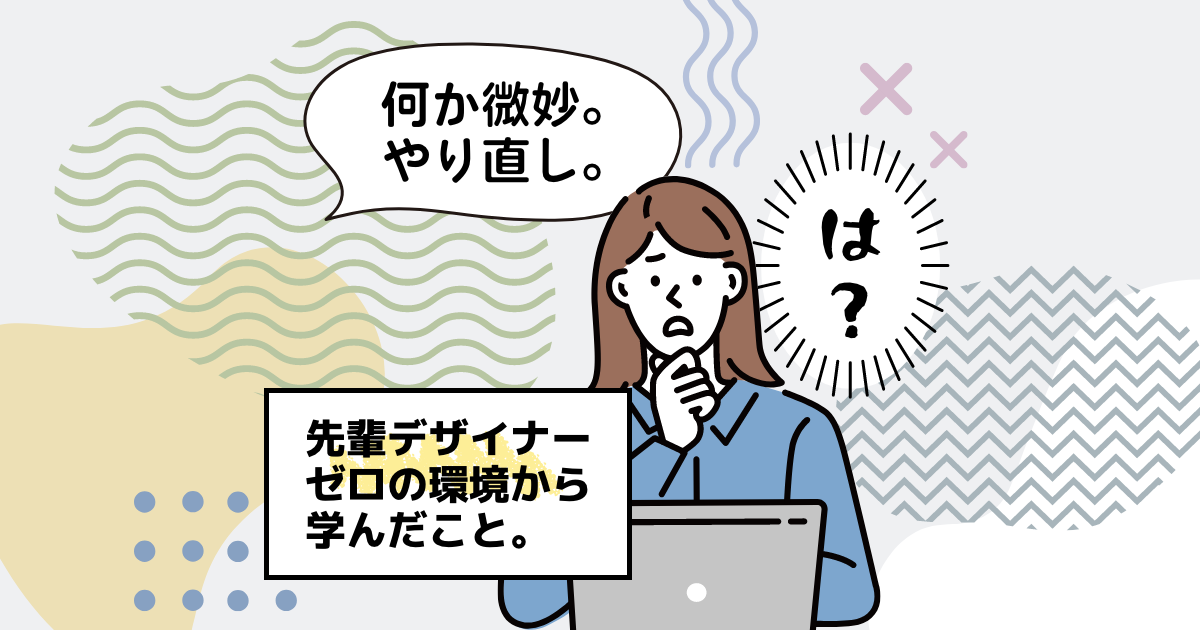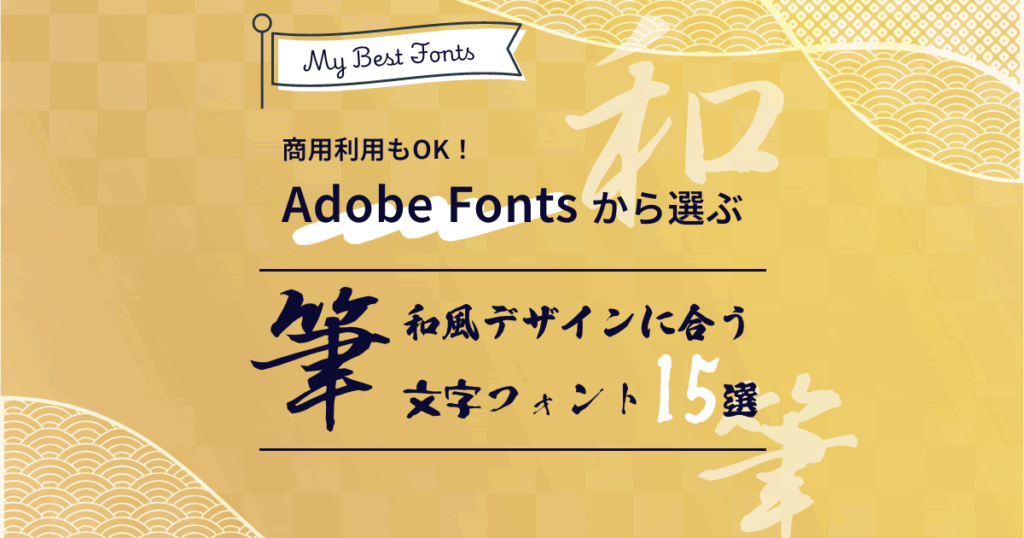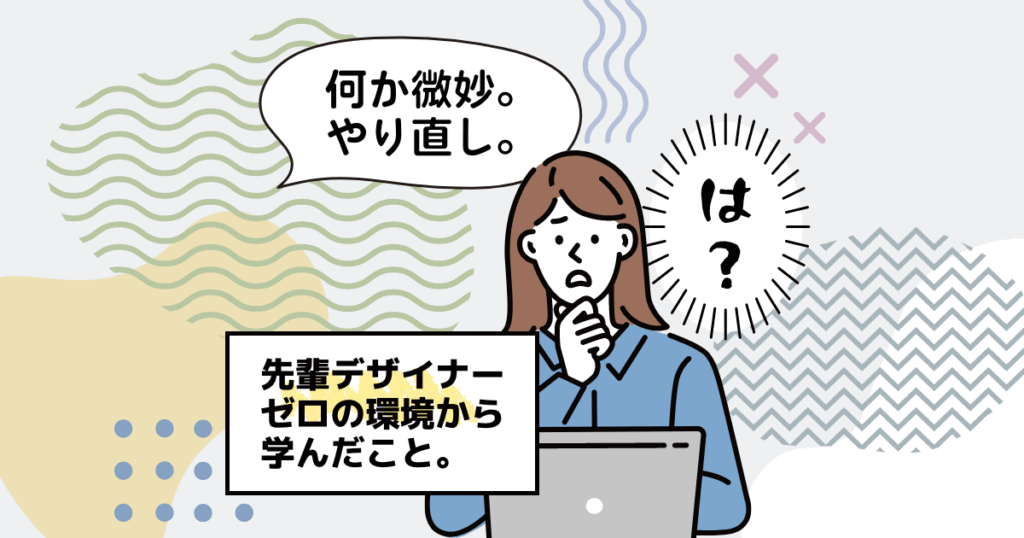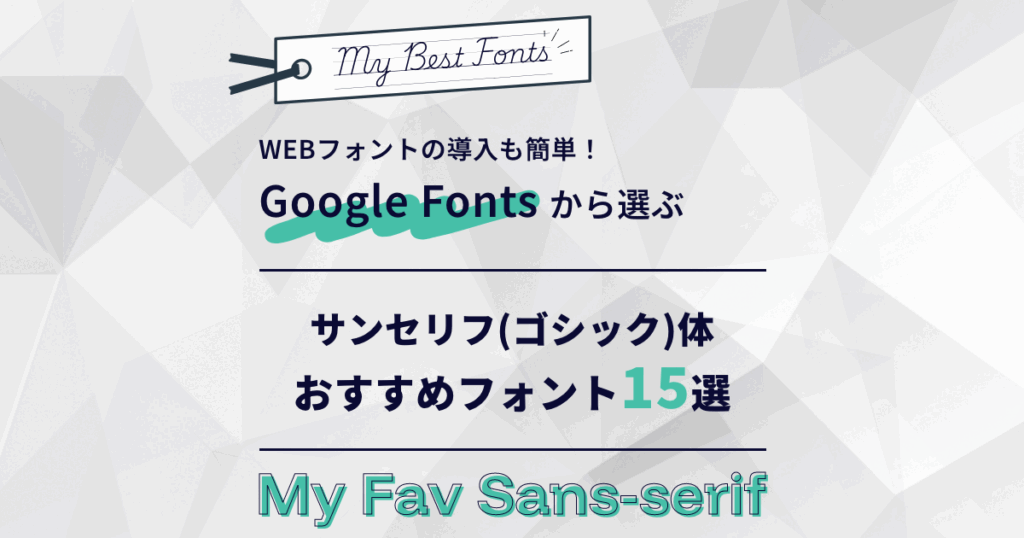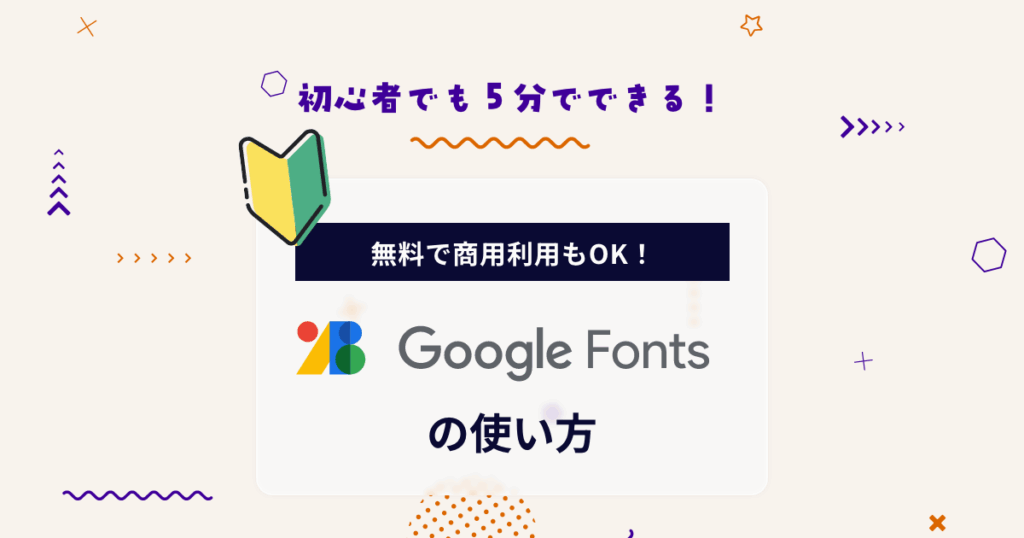WEBデザイナーの駆け出しの方の中には、
「デザイナーとして本当に成長していけるのか…」
「先輩にちゃんと教わらないと、実務レベルには到底追い付かないのではないか?」
と、伸び悩む方も多いのではないでしょうか。
もちろん、経験豊富な先輩デザイナーの元で学べる環境にいる方であれば、先輩方の技術を学びスキルを伸ばしていくのが一番の近道です。
しかしながら、手取り足取りデザインについて教えてもらえるような環境ではない場合の方が大多数だと思います。
ただでさえ絶対的な正解のないデザインの良し悪しを、自分の中で「これでいい」と判断するのは難しいことです。
そのような「デザイナーとして成長できるか?」という新人デザイナーさんにとってよくある不安について、記事にしてみました。
数をこなすことや常にトレンドに対してアンテナを貼ることは前提としてもちろん大切ですが、一歩踏み込んで「デザイナーとしての視野をどう広げるか」という観点からお話ししたいと思います。
目次
先輩デザイナー不在の環境でデザイナーになった話
私がWEBデザイナーとして初めて働いた会社は、もともとシステム開発系の企業でした。
WEB制作の部門が立ち上がったばかりで、チームには私一人しかおらず、社内にもデザイナーはいません。
そのため、デザインレビューをしてくれたのは、デザイン未経験の社長でした。
初めてデザイン業務に携わる私は、
「今はこの色がトレンドだからこういう色にした方がウケがいいよ」
「ユーザビリティの観点からも、このボタンはこう配置した方が使いやすいよ」
……そんなアドバイスを期待してしまうわけです。
ですが、実際に受けたレビューの大半がこんな感じでした。
「何か微妙。作り直して。」
「うーん、ちょっと違う気がする。何かイケてない。」
「具体的にどの辺が微妙でしたか?」
「最近のトレンドである○○○○を取り入れているので、私としてはこれがベストだと考えていますが…」
と言い返そうものなら、「何がダメなのか考えて、いいものへ作り直すのが自分の仕事でしょ?」と突っぱねられる日々でした。
当時は「は!?」と納得がいかず悔しい思いをしていたのですが、今思うと、この環境だからこそ学べたことが実はたくさんあったと感じています。
「何か微妙」の中にあった、ユーザー目線のリアル
正直、「デザインのことがわからない人にデザインの評価をできるわけがない」とふて腐れそうになった時期もありましたが、よくよく考え直してみました。
WEBデザインを届ける相手(ターゲット)とは誰なのか。
デザイナーに対象を絞ったコンペサイトや求人サイトでない限り、WEBサイトを閲覧するのは非デザイナーであるユーザーであることが大半です。
デザイン業務に集中していると、つい細かいテクニックや技法、トレンドを取り入れようとこだわりがちになります。
ですが、極端に言えば、「デザイナー同士にしか伝わらない良さ」にこだわると、真のターゲットに届きません。
そこで私は、「何となく微妙」というフィードバックも、「ユーザーとしての直感的な違和感がある」というサインではないか?と考えるようにしました。
たとえば、こんなフィードバックがあったとします。
「何となくインパクトが弱い気がする」
→商品の魅力がきちんと視線を引けていないのかも?
- 不要なあしらいや装飾的な背景を削って、商材にフォーカスさせた
- 見出しのキャッチコピーを短文にし、第一印象を改善させた
「思ってた感じと違う」
→世界観や印象がずれているということ?
- テーマカラーやフォントのトーン、写真の雰囲気をイメージに合わせて再検討
- クライアントの話を深掘りし、まずはFVだけでもしっかりと認識をすり合わせる
「なんか見づらい」
→視線の流れやタイポグラフィがうまく機能していない可能性
- 余白の取り方を見直し、要素をグルーピング
- 情報の優先順位を決め直す
- フォントサイズや行間、文字色や、見出しと本文のメリハリを強調
このように、「非デザイナー」の意見を「抽象的でわからない!」と決め付けず、むしろ「このフィードバックはエンドユーザーの意見そのものなんだ」と認識し、その違和感をまず言語化することから始めるようにしました。
「なんか違う」に自分なりの答えを出す
非デザイナーからのふんわりしたフィードバックを「ユーザーの声」として捉えるようになってからは、その違和感を解消するために、自分なりの「読み取り方」と「改善方法」を模索するようになりました。
自分なりの仮説を立てて、原因を掘り下げる
「何が『違う』と感じさせたのか?」
「どの部分が伝わっていないのか?」
という問いを、自分自身に向けるようになりました。
原因を仮説としていくつか出し、それぞれの案を試しながら「改善の精度」を上げていく流れです。
修正案は複数出し、比較しながら説明できるようにする
AがダメならB、BがダメならC…というのではなく、思い付いた仮説に基づき複数の修正案を出すことを意識するようになりました。
・構成は変えずに色味を修正したもの
・文字やボタンの配置を変えてみたもの
・画像そのものを差し替えてみたもの
など、「どこをどう変えたのか」「なぜこの方向性がいいと思うのか」という論理的な説明やプレゼン力を練習する絶好の機会だと思うように。
そうすると、「この案だとしっくりくる!」というリアクションをもらいやすくなりました。
誰かに「正解」を教えてもらえる環境ではなかったからこそ、「自分で考える力」と「意図を伝える力」を培うことができたのだと思います。
抽象的なフィードバックは、ユーザー目線をより意識できるチャンスでもあります。
デザインを見るのは「プロ」ではなく「伝えたい相手」
デザイナーとして経験を積むほど、「デザインの良し悪し」はプロ同士で語られるものだと思いがちです。
でも、実際にWEBサイトを見るのは、「そのサイトを必要とするエンドユーザー」です。
違和感は、ユーザーの「響かない」「わかりにくい」というサイン
「なんか微妙」「ちょっと違う」といった感覚的なフィードバックは、「プロ目線では気付きにくい違和感」を拾っていることがあると気付きました。
・「伝えたいメッセージが一目で伝わらない」
・「情報が散らかっていて、見る側が迷う」
・「空気感や印象が、目的やターゲットと合っていない」
といった、「直感的にわかりにくい」という感覚は決して無視できません。
デザインは「通じなければ意味がない」
どれだけ丁寧に装飾されていても、どれだけ最新の技術や理論を取り入れていても、それが伝えたい相手に届いていなければ、意味がない。
たとえば、言葉を美しく並べただけのポエムのような文章が、読み手に伝わらなければ、ただの自己満足で終わってしまうように。
デザインもまた、「伝えるための表現」になっていなければ、成立しないのだと気付きました。
私が実際にやってみて効果的だったこと
ユーザー視点を育てるには、「自分以外の目」でデザインを見る機会を作ることがとても大切です。
さらに、非デザイナーの視点も、「デザインがわかっていない人の意見だから」と切り捨てるにはあまりにももったいありません。
特に私がよくデザインを見てもらっていたのは、以下のような方々です。
- 直属の上司でもある社長
- 案件の仲介をしてくれる営業の方
- 案件に直接は関わらない事務・総務のスタッフ
デザインの知識がないからこそ、「第一印象はどうでしたか?」「どこが気になりましたか?」といったシンプルな問いに対して、リアルなユーザー視点での反応が返ってくることが多く、とても参考になりました。
※もちろん、案件内容や守秘義務には十分に配慮する必要があります。
先輩ゼロの環境でも、ここまで来られた
毎日のように「なんか違う」「微妙」と言われ続けながら、具体的な正解もわからないまま試行錯誤を重ねる日々でした。
ですが、振り返ってみるとあの環境だったからこそ、「誰かに頼らず考える力」と「伝える力」が育ったのだと思います。
デザインに正解はありません。
だからこそ、受け取る相手の反応に耳をすまし、抽象的な違和感の中にある「伝わらない理由」を探ること。
それを続けていくうちに、少しずつでも「伝えるデザイン」に近付けていけます。
- ちゃんと教えてくれる先輩がいない…
- 自分のデザインがいいのか悪いのか、自分ではわからない
- 「なんか違う」と言われるたびに自信をなくしそうになる
…とお悩みの新人デザイナーさんにとって、少しでも参考になれば幸いです。